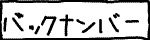『横山健の別に危なくないコラム』
Vol.107
僕とツネちゃんは1991年の夏に出会った。Hi-STANDARD 結成のためにスタジオに集合した時が初対面だった。
ハイスタは4人組だった。すぐに辞めることになるボーカルの人とナンちゃんが新しくバンドを組もうというところから始まった。僕とナンちゃんとはお互いに前のバンドで対バンをしていて、すでにライブハウス仲間だった。僕は下北沢のライブハウスで働いていたので、そこに出入りするバンドマンの動向に詳しかった。そんな僕のところにナンちゃんが「新しくバンド組むんだけど、誰か体が空いてるギタリストいない?誰かがバンドを辞めたとかいう情報ない?」と相談に来たのだが、当時やっていたバンドに限界を感じていた僕が「おもしろそうだからオレやりたい!」と立候補した。「ドラムは誰がやんの?」と聞くと、どうやらボーカルの人が連れてくるとのことだった。ナンちゃんはそのドラム君を知っていたようだが、僕には聞き覚えのない名前だった。
そして1991年の長くて暑い夏の日、4人でスタジオに集まった。ツネちゃんは20才になったばかり、ナンちゃんは21才、ナンちゃんの一学年上の僕も誕生日を迎える前で21才だった。
その日、ドラム君は僕のことが気に入らなかったらしく、一言も口をきいてくれなかった。もの凄く不機嫌なのが初対面でもわかるほど、露骨に不機嫌だった。
後にわかるのだが、ツネちゃんはもっとシブい音楽をやるもんだと思ってスタジオに来たらしい。ツネちゃんも、ボーカルとベースは知っているが、ギターはどんな人なんだろう?と謎だったようだ。ボーカルの人に「ギターはどんな人?」と聞くと「うるさい人だよ」と答えられたらしい。ツネちゃんはてっきり音楽や演奏にうるさい人だと、それなら大歓迎だと思っていたらしい。
ところが当日現れたのは、メッシュキャップを被って短パンを履いてネルシャツを腰に巻くという80年代のスケーターファッション全開のやつで、なにがうるさいって口やギターの音がうるさい、これは話が違う、と。そりゃ口をきいてくれなかったわけだ。
そしてツネちゃんは2度目の練習をバックレた。
自分のせいでツネちゃんが不機嫌だったとは勘付いていなかった僕、「あのドラム君、ダメじゃない?」と、そして別のドラムを引き入れるためにナンちゃんと話した。僕にはちょうどバンドを辞めそうな、めっちゃキャラが立っててドラミングも派手な友達がいた。僕はこの新しいバンドは U.S. ハードコアタイプの楽曲をやるもんだと思っていたので、その僕の友人ならドンピシャでハマる。そいつに当たってみてもいいかい?と聞いた。
ところがナンちゃんは「うーん、オレはもう少しツネくんでやってみたいんだよねぇ」と言う。賛同を得られないのならしょうがない、僕も「不機嫌なドラム君」の様子をしばらく見ることにした。
とても不思議だった。ナンちゃんだってツネちゃんと初めて会ってから、そんなに日が経ってないはずなのに。そんなに仲が良いわけでもないはずなのに。なんでそんなにツネちゃんの肩を持つ??とても不思議だった。
もしこの時、僕が友人のドラマーをもっと強引に推していたら……当然いまの Hi-STANDARD はない。
運命とはもっと不思議なものだ。
その直後に家を勘当され行き場を失ったツネちゃんは、車で生活しながらスタジオにも来るようになった。結成から2ヶ月で初ライブをやることになった。オリジナル曲が4曲できたが、それでも持ち時間が余るので、カバーを2曲やることにした。初ライブの1曲目は The Damned の “Fish” のカバーだった。
若いヤツ同士が仲良くなるのに、そんなに時間は必要ない。ボーカルの人が僕達3人より上の世代だったこともあってか、練習の後に3人でつるむことが多くなり、すっかり仲間になった。ツネちゃんとは好きな音楽の話をいっぱいした。僕が The Blues Brothers が大好きだと語ったことが、不機嫌なドラム君の僕に対する壁を壊してくれたらしい。
2本ライブをやったところで年上のボーカルの人が辞め、バンド経験のないナンちゃんの地元の友達をボーカルに立てて92年の夏までやった。彼はとても良いやつだったが、ボーカル向きの性格ではなかった。僕はバンドに強烈なフロントマンが必要だと感じていた。「誰か強烈なボーカルと出会うまで3人でやろう。ナンちゃん前のバンドでベースボーカルやってたじゃん?」
こうして僕達は、皆さんが知る3人組になった。
3人組になってからは物事が上手く運び始めた。そしてなにより、いつも3人一緒だった。練習が終わった後も缶コーヒー片手に、新宿の道端に座り込んでミーティングという名の語り合いをした。
「ここでさ……こうして新宿のきったない道端に座り込みながらさ、音楽だけは世界に羽ばたいていったら……こんなにカッコいいことはないよねぇ」、僕達3人は夜な夜なそうやって、夢物語を語り合った。本当にただの夢物語だった。後にそれが実現するなんてこれっぽっちも思わず、しかし疑うこともせず、無限の可能性の中を泳ぎ始めていた。
僕とナンちゃんは野心家だったが、ツネちゃんはあまりそういう感じではなかった。バンドの運営は事実上僕とナンちゃんでやっていたが、必ずツネちゃんに意見を求め、3人全員がオッケーしないことには手を出さなかった。それは今に続くまでずっと守られてきた。
野心家ではない代わりに、ツネちゃんはその力を打ち上げの席でのチンコ芸で発揮していた。若いバンドには横のつながりが必要だ。それがないとよそのバンドの企画にも誘われない、つまりバンドが大きくなっていかない。僕達の周りの環境はそうだった。打ち上げなどは実はライブ以上に勝負の場、であった。そういった肝心な場面でツネちゃんのチンコ芸はもの凄い爆発力を誇った。その場にいたみんなを笑わせた。友達がたくさんでき、いろんなバンドの企画に誘われるようになった。日本のバンドもさることながら、NOFX や LAGWAGON のメンバーをも魅了した。僕達はツネちゃんのチンコ芸のおかげで成功した、と言ってもいいくらいのものだった。初期ハイスタの一番のストロングポイント、それすなわち、ツネのチンコ芸だ。
その芸に限らず、ツネちゃんはいつも僕とナンちゃんを笑わせてくれた。本人はそんなつもりはないかもしれない。本人は至ってマジメなのだが、なぜだかツネちゃんの身には笑えることが起こってしまう。いつまでたっても色褪せない笑えるエピソード、しょうもないエピソードばかりだ。酒の席で、楽屋で、日常で、ツネちゃんの話は笑える話しかない。警察沙汰も命に関わることもある。でも僕とナンちゃんはいつもそれを笑ってた。本当は笑えないことも多い。しかしツネちゃんがそれを起こしたかと思うと、なぜか笑い話になってしまうのだ。
いま毎日毎日、いろんなことを新しく思い出す。「ああ、あんなこともあったなぁ」「そういやぁ、こんなこともあったっけなぁ!」「忘れてたぜ……こんなこともやらかしやがった!」、たぶんツネちゃんの笑い話だけで、僕は本が一冊書ける。
僕はツネちゃんが大好きだった。ツネちゃんが僕のことをどう思ってたかは知らない、僕はツネちゃんが大好きだった。なんか、一生懸命に世話してやろうと思ってんのに全然懐かない、でもなんだかんだ僕達の後を付いてくるきったない野良犬みたいなツネちゃんが大好きだった。気難しくて、ちょっとプライドが高くて、どこか抜けてて、無軌道で、ドラムに対して真剣なツネちゃんが大好きだった。
ツネちゃんとの演奏は本当に楽しく、スリリングだった。僕はよくツネちゃんの方を向いてプレイした。曲の中で僕がいつもと違った小技を入れてみせると、ツネちゃんは嬉しそうにあの笑顔を浮かべ、ドラムのフレーズで返してきた。よくそうやって楽器でおしゃべりした。そしてナンちゃんのベース/ボーカル、僕のコーラスが絡まって曲としてのパーツが揃うと、まるでジェットコースターに乗っているかの如く、体がフワッとしたものだ。本当にマジックが起こっていたんだと思う。

「1995年8月、レコーディングのためにサンフランシスコに2週間滞在した。」
95年に出した 1st アルバム “Growing Up” がアメリカの Fat Wreck Chords からリリースされ、全世界に流通された。97年に出した 2nd アルバム “Angry Fist” は日本で当時一番信頼されていたチャートであるオリコンで、初登場4位につけた。安室奈美恵や小室哲哉などがチャートを席巻していた時代、英語で歌う激しい音楽にとってこれは快挙だった。音楽だけで食えるようになり、僕達は成功したと言っても良い。
90年代後半は、僕達は日本中、そして世界中を一緒に旅した。僕達が演奏した国は20を超える。レコーディングもアメリカでやり、気がつけば1年のうちの半分を海外で過ごしてた年もあった。そうやって僕達は時代を全速力で駆け抜けながら……疲弊していった。
もともと3人しかいなかったのに、バンドが大きくなるにつれて周りに人が多くなる。ミーティング場所は新宿の汚い道端から、綺麗なレコード会社のミーティング室へと変わった。話を3人だけでは決められなくなっていった。一緒に遊び回っていた時間は音楽やバンドの運営にのみ向けられる。エゴとエゴがぶつかる。バンドの成功に反比例するように、僕達3人の心の距離は離れていった。
3人で道端で夢を語っていた頃とは程遠く、バンドの在り方に対しての考え方の違いなども浮き彫りになった。バンドという「特殊な集団」の存在の根源が揺らいだ。お互いを大切にする気持ち、尊重する気持ちなど持てなくなった僕達3人は、それを解決する策を知らなかった。
しかし毎晩必死で、初めて訪れる国でプレイした。遮二無二プレイすることで、爆発寸前の問題を忘れたかったのかもしれない。
僕達は1999年にレコード会社/マネージメント会社から離れ、Pizza Of Death Records を設立し、独立した。周りは当然反対した。しかしいま思えば当時の僕達は、周りを敵に仕立て上げていただけだったのかもしれない。そうでもしないと3人お互いが敵になってしまいそうで、それを避けたかったのかもしれない。
グラグラと揺らぎながらも1999年にリリースした 3rd アルバム “Making The Road” は大成功し、独立したことへの高評価も相まって、僕達はその地位を不動のものにしたかのように思われた。しかし翌2000年、僕が抑うつ状態に陥り、8月に千葉マリンスタジアムで行われた “AIR JAM 2000” を最後に活動停止になった。
僕達3人は2000年夏に、一度散った。
散ってしまった3つのピースを集めるのに11年もの年月を要したわけだが、この理由を俯瞰的に語るなら、「なにが原因」とか「誰はやりたいと思っていた」とか、そんなようなものは核心を突いたものではなく、結局3人ともやる気にならなかったのだ。誰も進んで話し合いの場を持とうとか、ピースを集めてまたバンドを動かすための動きを積極的にしなかったのだから、それはそうなのだ。それぞれに言い分や正義があるだろうが、僕も、ナンちゃんも、そしてツネちゃんも、腹の底から「やりたい!」って思わなかった、これが核心ではなかろうか。
そして11年の間、僕達3人はまるで他人のように動いた。僕は Ken Yokoyama を始動させ、ナンちゃんは沖縄に移住した。ツネちゃんは様々なアーティストのレコーディングに参加するようになった。いわゆる「スタジオドラマー」だ。そして現 Learners のチャーベ君のソロ・ユニットである “CUBISMO GRAFICO FIVE” に参加した。
……時期が定かではないのだが、恐らく2000年代の中頃、「ツネちゃんが精神疾患を患った」と聞いた。すぐに会いに行けば良かったのだが、なんとなく気を遣ったのか、腰が引けたのか、連絡を取れずにそのまま何年も経った。
僕は2010年に Ken Yokoyama の4枚目のアルバム “Four” をリリースし、長いツアーに出た。そのツアーの富山と福井のライブにサポートアクトとして CUBISMO GRAFICO FIVE を呼んだ。久しぶりに会ったツネちゃんは、笑顔こそ浮かべていたものの、やはりなんとなく生気のない雰囲気だった。なんだか僕の知っているツネちゃんじゃないような気がした。そりゃ何年も会っていなかったのだし、別バンドで来ているのだし、なにしろ精神疾患を患ってしまったのだから当然なのだが、すごく複雑な気分になったのをよく覚えている。
その頃ツネちゃんが言っていたのが、「シンバルの音が形で見えるようになった。しかしある日それが消えてしまった」というものだった。どんなことでも笑ってきた僕でも、さすがにこれは笑えなかった。何が原因でそうなったかはわからない。
いまでは、この11年間にもっと連絡を取っておけば、会っておけばという後悔はある。ハイスタの再開がどうこうとか、そんなことのためではなく、ただただ一番身近なはずだった仲間として。後悔先に立たず、いまさらどうしようもないのだが。いや、やっぱりそういう行動を取れなかった理由もあるわけで。それがその時の本気だったわけで。しかし人生が全てが同じ線の上にあると仮定したなら、もし積極的に行動できていたら、現在は変わったものになっているかもしれない。「風が吹けば桶屋が儲かる」というか「蝶の羽ばたきが竜巻を引き起こす」というか……。考えても全く建設的じゃないのだが、思わず考えてしまう。

「福井で別れ際に撮った写真」
僕達は2011年の東日本大震災を期に再集結した。2011年に横浜スタジアムで、2012年には被災地の東北宮城県で Air Jam を開催した。
宮城での Air Jam 開催は再集結時の念願だったので、開催できたこと、Hi-STANDARD として人前に出て演奏できたことが嬉しかったし、誇らしくもあった。しかし3人の関係はというと、11年間の隙間を埋めるには至らなかった。あの日に演奏していたのは、間違いなく以前と同じ3人だった。一度散ったピースが再び揃っていたことは事実。しかし誤解を恐れずに言うと、その場に立つ資格を伴った「集団としての精神性」が欠けていた。それは観に来てくれた方々にとってはおそらくまるで問題ではなく、しかし僕にとっては大問題だった。そして僕は「90年代の自分達には戻れないのなら、新しい関係になるしかない」と、はっきりと自覚した。
とても繊細な課題だった。機会と時間が必要だった。僕達は不定期ではあるが、ちょいちょいスタジオに集まって、練習したり近況報告し合ったりする機会を作り始めた。
僕達3人がお互いを「かけがえのない存在」として尊重し合い始めたのは、実はこの時期なんじゃないか、と思う。ツネちゃんもナンちゃんも、明らかに以前とは違って見えた。ナンちゃんはとても僕とツネちゃんを尊重し、3人での居場所を必死で守ろうとし始めていた。ツネちゃんからは若かった頃の不機嫌さは消え、いつも明るい笑顔と態度を示すようになった。僕も変わっただろう。
僕達……と言うより僕とナンちゃんは、活動停止中の11年の間に周りの人間や公を巻き込み、大喧嘩した。もうお互いのことを必要としない人生になると思い込んでいたし、僕に至っては確信すらしていた。しかし動機や縁があり、再びバンドメンバーとして人前に出るためには、お互いを許し、さらに認め、徹底的に向き合う以外に道はなかった。ツネちゃんも自身のために、その場にいる必要があった。僕達は3年かけてそれを達成した。
そうしながら僕達は新曲作りに着手していた。いくつか新曲の種みたいなことを試し、次回の練習までにはそれを忘れる、そんなことを繰り返した。良い解釈をするなら、本当に新曲ができたかどうかはあまり問題ではなく、作ろうとすることそのもの、それにまつわる時間、もっと大きく言うと「ただ集まって会話しながらなにか作業する」という事実が大切だったのだ。
そしてある日、数年ぶりの新曲は遂にできた。”Another Starting Line” だ。このリリースは翌年まで待たなければならなかったが、新曲があるという事実は僕達を「90年代のバンド」から「現在進行形のバンド」に変えてくれた。2015年末には3本のイベントに参加したが、自信を持ってステージに立てた。
2016年にシングル “Another Starting Line”、翌17年には4枚目のアルバム “The Gift” をリリースし、アリーナツアーを敢行した。
“The Gift ツアー” は本当に楽しかった。そして興味深い体験だった。ツアーが始まった頃は、久しぶりのツアーということもあり、若干肩に力が入っていた。それぞれ背負うものが違ったのだろう、少しのバラバラ感は否めない空気だった。
僕達はライブ前になると、スタッフ全員に部屋から退出してもらい、3人だけで話す時間を必ず持つようにした。大袈裟に言うと、それは3人で精神を分け合うための時間と空間だった。これの効果が大きかったのだと思う。僕はツネちゃんにもナンちゃんにも「自分が調子悪くても、一人で何とかしようとせずに、他の二人を頼れ」と話した。おかしなもんだ、こんなの完全に根拠のない精神論だ。だってドラムの調子が悪かったら、僕にできることなど物理的に存在しない。しかしこういった精神論が通じてしまうのが、つまり「バンドであること」の証左なのだろう。僕達は同じ指標を見るようになり、ライブのたびにバンドとして強固になっていった。これは本当に肌で感じられ、バンドって生き物なんだなぁとつくづく感じた。
僕はこのツアーを大きな充実感とともに終えた。誰と比べるわけでもないのだが「ハイスタは世界一のロックンロールバンドだ」と思えた。本気でそう思えた。音楽なのだから勝ち負けがないことなんて分かっている。僕自身もどのバンドとも戦っていない。しかしなんの迷いも、矛盾も照れもなく、自然とそう思えた。
僕達は、世界一のロックンロールバンドだった。
翌18年には千葉マリンスタジアムにて “Air Jam 2018” を開催、年末には “The Gift Extra ツアー” を敢行した。僕達は17年に獲得した勢いをそのまま保持し、各地で我ながら素晴らしいライブができた。僕はツネちゃんとナンちゃんとバンドが出来ていることに感謝の気持ちでいっぱいだった。出会えたこと、3人で集団を形成できていること、一緒に音を鳴らせていること、全てに感謝し、二人を心の底から尊重し、誇らしく思った。
18年のツアー最終地点の沖縄2デイズを最後に、ハイスタはまた休眠期間に入った。これには大した理由はなく、数年ハイスタに力を入れたから、しばらくお休みしてそれぞれのことに集中しよう、という程度だ。そして2020年にはコロナ禍が全世界を襲い、ハイスタの再開はコロナの収束後にしようということになった。
1991年に生まれた恒岡 章、難波 章浩、横山 健という3人を擁する Hi-STANDARD という世界一のロックンロールバンドは2018年末に動きを止め、二度と同じ姿で人前に戻ることがなくなるとは、この時は微塵も思わなかった。
2022年にもなると動いているバンドも、休んでいるバンドも、「いつかはコロナに振り回される日々は終わる、それに向けてどうする?」と考えたことだろう。僕達もそうだった。幸い外部からもいくつか楽しそうなお誘いを受けたこともあり、なんだかコロナが明けたら忙しくなるぞ、そんな気がした。僕達3人はたまにウェブミーティングをしつつ、お互い元気なことを確認し合っていた。いただいた話が増えるに連れてウェブミーティングの頻度は増し、話は具体的になっていった。
まず第一歩として、僕達は2022年12月にたった1曲だけ、”I’M A RAT” という新曲をレコーディングした。そしてそれを披露するための場所として、出演オファーを受けた “SATANIC CARNIVAL 2023” を選んだ。

……僕には僕で、想いがあった。お互い顔を見るたびに思うことがあった。「みんな老けたなぁ」、そりゃそうだ。3人とも50才を超えて、老けないほうがおかしい。
これは僕個人の話だが、本当に年を取ったと思う。物覚えは悪くなり、Tシャツのサイズは M から L に変わり、顔つきも変わった。こういうことを通じて「人間って本当に老けるんだな。そりゃいつか死ぬよな」と感じる。事実53才だ。「実際の話……僕はいつまでできるだろうか」、そんなことをいつも考える。
思い返してみれば、僕はここ10年くらい、常に「自分の死」ということを意識して暮らしてきた。理由はわからない。しかしそれに対する意識は歳を重ねるごとに、もっと言うと一日一日を終えるたびに強いものになっていく。
僕にはバンドをやっていく上でのルールがあった。それは「Hi-STANDARD と Ken Yokoyama の活動をごっちゃにしないこと」。例えば「この期間は Hi-STANDARD で動く」となるのなら、それを Ken Yokoyama のメンバーに伝えて、やることがあるならその間にやろうと心の準備をしてもらうことが Ken Yokoyama のメンバーに対しての最低限の礼儀だと思っていた。もちろんそれは逆も然り。そしてそれは皆さんに対しての Hi-STANDARD/Ken Yokoyama の打ち出しとしてとても良いことだ、と思っていた。サポート・プレイヤーなら「今日はどこの街でこのバンド、明日は別の町で別のバンド」は大いにありだ。しかし両方のバンドのフルタイムメンバーでそれをやっちゃダメだ、両方のメンバーに対して申し訳ない。自分も整理がつかないし、なにしろきっと見てて節操ない。良いことはなにもないと思っていた。ナンちゃんもツネちゃんも僕のこのルールを、僕以上に尊重してくれた。
今年の初め頃だっただろうか……年を取った自分の姿を見て、もうそんなルールを忘れたいと思った。そしてウェブミーティングの場でこう話した。「オレはもう53じゃない?あと何年できるかと考えてしまうんだ。このまま2つのバンドの活動期間を分けさせてもらっていたんじゃ、あっという間に60や70になって、体も動かなくなって、もっとハイスタをやっておきゃ良かったって思う気がする。それどころか、もういつ死ぬかわかんないしね。明日ポックリ死んじゃうかもしれないし、ハハハ」という感じだったと思う。つまり「今週は Hi-STANDARD、来週は Ken Yokoyama でもいいから、両方ともできる限りやりたい」と伝えた。二人は僕のこの大きな心変わりを喜んでくれて、それを実践していこうということになった。幸いにして、いただいた話もいっぱいある。同時に2023年か24年のどこかで音源をリリースし、ツアーをする予定が固まっていった。
ツネちゃんはその後のグループ LINE に「忙しくなるぞー!」と書き込んだ。
ここまでが僕達3人のストーリー。
そのすぐ後、2023年2月14日、恒岡 章は亡くなった。
僕はその日、Ken Yokoyama のレコーディングでスタジオにいた。ギターソロを録る日だったので、丸一日が自分の出番という日だった。夕方に休憩を取り携帯を覗くと、ナンちゃんから大至急連絡くれという LINE と着信が残されていた。ナンちゃんは僕がレコーディング中だと知っていたはずで、そういう時はどんな用件だろうと僕に無理に連絡を取ろうとはしなかった。なんだかおかしいなぁと思った。一応 LINE で「今日はレコーディングだよ」と返すと「ツネちゃんが」と一言だけ返ってきた。
猛烈にイヤな予感がした。しかし今までに警察に捕まったり、生命に関わるような大事故を起こしたりしてきたツネちゃん。これもきっとそんなことだろう、むしろその程度であってくれと祈るような気持ちで外に駆け出て、ナンちゃんに電話した。しかし告げられたのは、ツネちゃんが亡くなったということだった。体からスーッと力が抜けていき、ヘナヘナとその場に座り込んでしまった。ちなみにそれ以降どんな内容の会話をしたのか、全く覚えていない。
ただ分かったことは、レコーディングを中断してツネちゃんに会いに行っても、その夜は会えないということ。ツネちゃんの家族に会おうとしても迷惑になりそうだ、ということ。動くに動けない。
何時間かボーッとしてしまった。メンバーが「今日はもう止めて、とりあえず家に帰ったほうが良い」と気遣ってくれたが、結局僕はレコーディングを再開した。まず「Better Left Unsaid」のギターソロを録った。音源のソロにわけがわからないその時の感情が溢れているはずだ。その後もおそらく結構深い時間まで続けたはずだ。ギターソロをいくつも録った。
翌日の昼頃にツネちゃんと会えるというので、ナンちゃんと合流して会いに行った。ツネちゃんは棺に収まって寝ているようだった。声をかけたが返事はない。まぁでも若い時のツネちゃんなんて、酔っ払って寝ちゃうとほっぺたを引っ叩いたってまず起きなかったので、それに似てる。しかし顔に触れると冷たかった。本当に死んでしまっていた。一気に何かがこみ上げてきた。嗚咽が抑えられなくなった。僕はクソほど泣いた。ナンちゃんと二人して、クソほど泣いた。どれくらい泣いたかわからないくらい泣いた。
僕達3人は、間違いなく同じ夢を見ていたはずだ。2011年の再集結以降、以前とは違う新しい Hi-STANDARD の在り方を獲得していく中で、空白の11年間を「畳んでいた」と形容するなら、「二度と畳むことはない」と思っていたはずだ。止まりはすれども決して畳まない、と思っていたはずだ。生きている以上 Hi-STANDARD であり続けると、3人それぞれが心に持ったはずだ。しかしそれは「3人の内の誰かが死ぬ日まで決して畳まない」を意味していた。こんなに早くその日がやってくるなんて考えもしなかった。僕とナンちゃんは決めなければいけなかった。
二人で棺の両脇に立ち、手をつないで、ツネちゃんの胸の上に乗せた。そして「ツネちゃん、オレ達は進むよ」と語りかけた。この時まだ二人でこの先どうしようという話はしていなかったが、図らずも話し合う前に気持ちは決まっていた。
二人ともこのまま終われない。ツネちゃんがいなかったらハイスタじゃない、そんなの良くわかってる。でも僕とナンちゃんは、とてもじゃないがこのままでは終われない。策なんて後で考える。とにかくこのままじゃ絶対に終われない。僕達二人はこの先も生きていかなければいけない。少なくとも残った二人の内どちらかがくたばるまで終われない。
どのくらい時間が経ったのか記憶にない、僕はまたレコーディングスタジオに向かったのだが、そんなに強くもない夕方の西日がビルの谷間に落ちていくところだった。
数日後に近親者/音楽関係者のみでお通夜が営まれた。たくさんの方が弔問に訪れてくれた。ツネちゃんの友人達、ツネちゃんがレコーディングに参加したアーティストの方々、同世代のバンドマン、後輩のバンドマン。ツアー先から急遽向かってくれたバンドマン。ドラム関係の方々。皆さん忙しい中来てくれた。「ツネちゃんは愛されてるんだなぁ」と感じずにはいられなかった。本当にツネちゃんはみんなに愛されていた。ツネちゃんのことを悪く言う人には出会ったことがない。
翌日に葬儀が執り行われた。近親者とごく近しい友人のみが出席した。皆さんにお気遣いいただいて、少しだけ3人になる時間をいただけた。あまり会話はない。静かだが、きっと僕達3人はいろんなことを話したんだと思う。
出棺の際、僕とナンちゃんが棺桶の左右の先頭を持った。いつかこんな時だって来ると漠然とは考えていたが、こんなに早く来るとは。ツネちゃんの棺が閉じられる際、ナンちゃんはハイスタの3人の写真を入れた。
ツネちゃんの棺が火葬炉に入る瞬間、親戚の方が泣き声で「あきらーーー!」と叫んだ。そうだよツネちゃん、年老いた親戚の方より早く逝くなんて……でもツネちゃんの肉体はこれが限界だったんだね。
ツネちゃんは荼毘に付された。
ナンちゃんは、きっと本人は自覚はないだろうが、葬儀の間ずっと僕を探し、僕の隣りにいた。きっと猛烈に心細かったのだろう。オレはタバコを吸うので喫煙所にいくのだが、タバコを吸わないナンちゃんも付いてきてズーッと僕と一緒にいた。
その喫煙所で今後の Hi-STANDARD の話をした。数日の間に「続けていこう」という共通の気持ちは持てたが、「さて、どうやるのか」、きっとナンちゃんはそれが見えなくて不安だった。新しいドラムの話、やってみたい音楽の話、そういった希望のある話をしないと落ち着かない様子だった。でも実際はその場ではなにも決められることはない。そんなナンちゃんの堂々巡りの不安は手に取るようにわかった。
僕は「どうなろうと……たとえボロボロになったとしても、その姿をみんなに見てもらえばいいんじゃないかな」と伝えた。ナンちゃんは納得して、それがナンちゃんにとって「続けていく」ための最終的な決断になった様子だった。
ベストを求めて続けていくことは当たり前だが、結果失敗して今まで築いてきたハイスタを台無しにしたって、そりゃしょうがない。僕個人的には「やっぱハイスタはツネさん以外のドラムでやらない方がよかったんじゃないかな」、「ハイスタは晩節を汚したね」、そんなような評価を将来的に受けたとしても、それもそれで良いと思っている。
皆さんが慣れ親しんだトライアングルは終わってしまった。新しいものを作るしかない。もしかしたら……新しいものがさらに良いトライアングルになるかもしれない。
今後のことは誰にもわからない。誰も答えを持っていない。
結果は結果、恐れずに踏み出すのみだ。
僕達は、ツネちゃんの遺作になってしまった「I’M A RAT」をリリースした。この出来をツネちゃんもとても喜んでいた。音源を聴いてもらえばわかるが、ツネちゃんのドラムはキレキレだった。レコーディングのテクノロジーが進化した現在でも、コンピューターではあのドラムのカッコ良さは出せない。人力でしか出し得ない正体不明のなにかが、聴く人の耳を釘付けにするのだ。
僕はこのレコーディングの際に……こんなことを思った。ドラムとベースはレコーディング初日に同時に録った。ギター録りはその翌日だったので、ドラムとベースだけの音源をもらって、家に戻って聴いていた。「ハイスタってすごいすごい言われるけど……やっぱすごい。この二人は本当にすごい人達なんだよ」、そう思った。なにがどうすごいのか、言語化は難しい。単純に「カッコいい」のだ。「とんでもなくカッコいい」のだ。「カッコいい」ことをサラッとやってのけちゃうって、それってすごいじゃないか?つくづく思った。腹の底から思った。ハイスタだからすごいんじゃない、すごいからハイスタになったのだ。
ツネちゃんのドラムは、以前の音源にも増して、さらに歌いまくっていた。そう、ツネちゃんのドラムは「歌う」のだ。
「歌うツネちゃんの音を永遠に閉じ込める」ことに成功したと思う。
配信用のジャケットは「経費削減だ」と言って僕が勝手に描いた。この曲を練習し始めた11月くらいには描き上がっていたのではないだろうか。ツネちゃんに見せたら、これもすごく「カッコいいね」と褒めてくれた。なのでツネちゃんの遺作としては相応しくないかもしれないが、彼が認めてくれたものだから、このままジャケットにすることにした。
音の方もそうだ。ミックスが終わった数日後、ナンちゃんは自分のベースの音のおいしいところがもう少し欲しいと思い始めたようで、リミックスをしたいと言った。僕は「トコトンやろうよ、一度気になってしまったら放っておくわけにはいかないっしょ」とリミックスに賛成した。ミックスとはとても繊細な作業で、ただ足りないと思ったところだけ足せば良いというものでもない。足すと全体のバランスを壊してしまい、一からやり直しなんてこともある。でも僕もツネちゃんも GO サインを出した。結果さらに良いものになった。僕もツネちゃんも喜んだ。
そしてツネちゃん亡き後、ナンちゃんが「ツネちゃんのコーラスと最後のドラムのロール、もう少し大きくしない?」と再々ミックスを提案した。僕はこれには賛成できなかった。ツネちゃんと最後に OK を出したものでいいんじゃないか、と言った。もちろんツネちゃんの音を上げたくなる気持ちは痛いほどわかる。ナンちゃんの提案もツネちゃんに対する愛だし、僕のそのまま残そうというのもツネちゃんに対する愛だ。
SATANIC CARNIVAL 2023 への参加も発表になった。SATANIC CARNIVAL は友人のドラマー数人の力を借りて参加することにした。
具体的にどう立て直していくかは SATANIC CARNIVAL が終わってから考える。ナンちゃんとじっくりあれこれ考えて、行動しようと思う。また報告できることができたら、その都度させてもらいたい。
僕は……今年に入ってからずっと忙しくしていた。ツネちゃんが亡くなった2月も、先述した通りレコーディングの真っ最中で、それで気が紛れた部分もあったかもしれない。しかしそれでも「いまの自分はおかしい」と感じる瞬間は多々あった。なんというか、物の感じ方が鈍くなって、心のひだのようなものが無くなる感覚というか。うまく言語化できないのだが、とにかく明らかに自分がおかしいと感じる日が何日もあった。受け止め切れないショックを受けると人間こうなるのかぁ、もしかしたら本能が守ってくれてんのかなぁ、人間ってすげぇなぁなんて思ったりしてた。そんな中でも Ken Yokoyama のレコーディングを完了させ、自分のやるべきことに必死で向き合った気がする。向き合えるものがあって良かった。
3月から4月にかけて、やっとライブハウスに戻り「Feel The Vibes ツアー」を敢行している。このツアーが始まり、3年半ぶりにコロナ前と変わらぬカオスなライブを展開し、皆さんの大合唱を聴き、音に飢えた表情を見て「ああ……オレは生きてる」と実感できた。僕は毎晩ツネちゃんのことを思って、ツネちゃんも連れてライブしている。毎晩憑き物が落ちていく感じがした。このツアーに来てくださった皆さんに、僕は救われたかもしれない。いや,救われた。ありがとう。
そして……なぜこんな長ったらしい文章を書いているのか。ここまで書いたものを読み返すと、我ながら異様に淡々としている。そこから「なにか区切りをつけようとしている自分」の姿が浮かぶ。
人生にはいろんなことが起こる。起こってしまったことはしょうがない。生まれる命もありゃ、当然消えていく命だってある。しかしそんな真っ当な話では割り切れないものを、僕は背負った。それを振り払おうとしているに違いない。
僕は弱い人間だ。大きなものを背負ったまま前に歩いていけない。降ろさないといけない。そうしようとしてるに違いない。ごめんツネちゃん、僕はいかなきゃいけないから、悪いけど降りてくれ。
そんな気持ちを察してくれたのか、四十九日を迎えるほんの数日前、ツネちゃんは僕の夢に出てきた。夢の中のツネちゃんは、生きているのだが目は開けない。なんとも変な登場の仕方だったが、イヤな気はしなかった。むしろ僕は「ツネちゃんらしいな」と思った。きっとしばしの別れの挨拶をしに来てくれたのだろう。あとはどのくらいかかるかわかんないけど、きっと時が僕を癒してくれる。
癒えたらツネちゃん、もっと楽しい夢に出てきてよ。昔みたいに笑かしてよ。チンコ芸見せてよ。そうだ、娘ちゃん達がいるからそういうの止めたんだよね。オレの子どもはみんな男だからさ、その気持ちわかんないんだよな。ツネちゃんつまんねぇ大人になっちまったなぁってよく言ってたよね。それ言った時のツネちゃんの苦笑いが浮かぶよ。じゃあオレの観葉植物の悩みを聞いてよ。若い時みたいに、あてもなくドライブしようよ。湘南行こうよ、湘南。一緒にバンド組む?でも本当はうるさいギターは嫌いなんでしょ?でもよく嬉しそうな顔してくれたじゃーん。またあの笑顔見せてよ。また楽器でおしゃべりしようよ。正直に言って、いなくなった気がしないんだよな。生きてようが死んでようが、オレ達そんな間柄じゃないよね。
オレ達はハタチそこそこで出会ってるから、幼馴染みとまではいかないけど、まだ楽器を始めて数年しかたってなかったじゃん?ミュージシャンとしては幼稚園児とか小学校低学年くらいなもんだったわけよ。だからミュージシャンとしては幼馴染みだよね。言葉は喋るけどけどまだちゃんと感情を伝えられないっつーかね。オレ達まだバブバブのヒヨヒヨだったのよ。そこから一緒にいろんなこと覚えて、一緒にいろんな経験して、一緒に社会に出てったんじゃん?大きくなってさ。だからさ、オレはハイスタという場所は故郷みたいなもんだと思ってるよ。っつーことは、故郷に帰ってくればいつでもツネちゃんと会えるわけよ。まぁ帰らなくたっていつも会えるけどね。心の中でね。
しかし会えてよかったぜ、ツネちゃん。一緒に駆け抜けたね。考えてみ?一緒にとんでもないことをしでかしたんだぜ?楽しかったよ。オレはまだやりたいことがあるし、こっちで過ごすよ。ゆっくり休んでて。
愛してるぜ、ツネちゃん。

「ボクの一番好きな写真。ツネちゃん、またね。」
2023.04.20