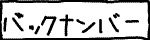フリーライター石井恵梨子の
酒と泪と育児とロック
Vol.33
地元の鹿児島で今月16日から、東京では10月15日から、大阪では11月5日からの公開が決まっているWALK INN FES!の映画『素晴らしき日々も狼狽える』( https://www.walkinntv.com )。前編では主催者・野間太一さんのキャリアをメインに話を進めましたが、後半はいよいよ作品の内容に迫ります。監督の安田潤司さんは80’Sジャパニーズ・ハードコアのドキュメント『ちょっとの雨ならがまん』を撮ったことで知られる映像作家ですが、彼はなぜこの小さなフェスに興味を持ち、「これが日本で一番先を行っている」とまで考えるようになったのか。フェスやイベントが全国各地に散らばり、地元の経済活性化の役割を担うと言われる時代に、では本当に必要なのはどんなことなのか。太一くん、安田監督、お話を聞かせてください!

一一2014年に始まり、そこから発展していったWALK INN FES!。監督の安田さんはそのスタートをどんなふうに見ていましたか?
安田潤司:僕、1回目は行ってないんですよ。2015年から広告で見かけるようになって、なんか面白そうだなとは思ってて、ちゃんと行ったのは2017年。そこで驚いた。なんか、いい意味でユルかったんですね。
野間太一:ははははは。
安田:2017年ってフェスの規模は大きくなっていって、メジャーのバンドも増えて、登り調子で拡大していった時期なんですよ。にも関わらず、意外にちゃんといい隙間があるなぁって。あとトイレに入った時かな、「ルールはないけどモラルは守ろう」みたいな張り紙があって。決め事を明文化しないで、自分たちで全体を意識しつつ、お互いの距離感とか自由に責任を持ってやろうっていう、そのユルさが良かったな。行政とか巻き込んで続けながら、この空気を維持できてるのもすごいなって。
一一どういう意味ですか?
安田:僕、行政の仕事もしていたので、田舎の町おこしイベントもいっぱい見てるんです。盆踊り的なやつ。カラオケがあって、フラダンスがあって、若い子向けのダンスとかもあって、あとは地元の芸人呼んで、バンドも一組くらい呼ぶ。そういうのはよくあるんですね。でもそこには当然、若い人が飛びつくようなストリート的センスもファッション的センスもない。まぁ格好いいか悪いかで言うと、若者的にはものすごくダサいものになる(笑)。かといって、田舎の祭りでオシャレなストリート・センスを極めようとすると、今度は地元の人たちが弾かれるんですよ。主催者としても参加者としても弾かれる。これが地方のイベントの限界点っていうか。
野間:ははは。すごい話だなぁ。
安田:でも太一は、ストリートの格好よさを維持したまま、年々いろいろなローカルのもの取り入れていくんです。ミックスさせて、適度な隙間と距離感を持たせたまま、そのどれも悪くないように見せるセンスがある。たとえば地元自治体が「うちの街はこんなことやってます」ってブース展開してるけど、近くに大作戦のテントがあって、その隣ではストリートアーティストが絵を描いている。全部混ざってるんだけど、配置とかバランスをしっかり考えてるから、フェスとしてはちゃんとオシャレに見える。
一一へぇ。それは主催者として意識的にやってるんですか?
野間:意識的……うん、やってきましたね。本来は責任が伴うのが自由だし、第一線で動いてるバンドなら「自由=責任感」ってわかってると思うんだけど。地方で「自由」って言い始めると、ほんと何でもあり、責任感なしの祭りになっていく。これが一番難しいところで。だからローカルのイベントってやっぱり難しいんですよ。メジャーのバンドを10組ブッキングしたほうが明らかに楽。だけど、地方バンドのブッキングを中心にしながらやっていく、できるだけみんなに自由って思わせるように、どこも窮屈に感じないようにやってもらう。それはずっと考えてました。

一一それ、言うのは簡単だけど実行するには難しくないですか?
野間:難しい(笑)。だからめちゃくちゃ喋ってます。直接話すことがやっぱ一番大変ですが大事ですね。地元の人たちと365日コミュニケーション取ってます。
一一話し続ければ、イベントは格好よくなっていきますか。
野間:絶対なっていきますね。結局みんな、僕もそうだけど、話してるうちにコロコロ変わるじゃないですか。フェスの準備って10ヶ月前から始まるんですけど、飲食店や雑貨屋さんやバンドだったり、それぞれ地元の人たちのコンテンツがたくさんある中、それを収めなきゃいけないから、10ヶ月前の熱いエネルギーが当日まで変わらず進むことはまずないですね。「あと何ヶ月、なんか変わったことあります?」って言っていくうちに、流れもできていく。たぶん「私のことをちゃんと見てくれてるんだな」っていう安心感もあるんじゃないかな。「イベントやるから出て!」「ハイ終わりです」だと寂しいでしょ。だから言い方悪いですけど、できるだけ相手をしてあげる(笑)。できるだけ喋り続けていく。そのほうが僕も面白いし、アガっていけるんですよね。
安田:WALK INN FES!の面白さって、まぁ太一の面白さですけど、基本的にはオープンソースなんです。WALK INN FES!は何も隠さないし、やり方も動きも正直だから。それ見てると、これは日本のどこにでも行けるなと思ったんですよ。地方の人たちが真似しようと思ったらできる。もちろん細かいところは本人次第だから、一朝一夕には真似できない。だけど時間かけて地元とコミットしながらやれば、これは誰にでも創っていけるなと。それがこの映画を撮ろうと思った動機のひとつでしたね。
一一いまやフェスなんて全国各地にある時代ですけど。
安田:そう。でも田舎で、スポンサーもつけないで、地元のバンドがいっぱい出て、人気のゲストバンドも出てる。都会のものと田舎の風土に垣根を作らない、その2つがきれいに融合されたフェスって、そうそうないですよね。だけどこれは規模に関わらずどこでもできること。それが日本中いろんなところにできて、それ自体がハブになってつながっていったら面白いなと思う。だからなんとかこの記録を残して、見たみんなが真似してくれないかなって。そういう思いはありましたね。だから映画の中では等しく扱ってるんですよ。ブラフマンとか健さん、地元のバンド、どっちのほうが上だっていう見せ方を僕はしてないんです。もちろんアーティストとしてのオーラとか表現力の差はあるにしても。

一一そこは伝わります。みんな等しく個として扱われている。
安田:太一自身がそういう見方なんですよ。さっき「田舎とか都会ってあんまり関係ない」って言ったけど、「都会っていう人間は存在しないでしょ? 田舎っていう人間もいないでしょ? いるのはみんな個人でしょ?」っていう意識で動いてる。だから全員が主人公の群像劇みたいな映画にしたいなと思いましたね。撮りながら初めて「あぁ、WALK INN FES!ってこういうことなんだ」って僕も理解していったし。
一一これは一般的なフェスのドキュメントじゃないですよね。もっとなんか、人の営みの話だと私には思えました。
安田:人の営み。そうですね。個人しか撮ってないですからね。普通、たくさんの素材から創るならフェスのライブムービーなんでしょうけど、そこにはフォーカスしてない。太一とも最初から「普通のライブ映画作っても全然面白くないでしょ」って話してた。最初、女の子が石井さんの本(書籍「東北ライブハウス大作戦 -繋ぐ-」)を読んでるじゃないですか。
一一はい。びっくりしました(笑)。
安田:よく見ないとわかんないんですけど、あれ、黄色いマーカーが引いてあるんです。それは実際にいるスタッフの女の子の持ち物で。10代でWALK INN FES!に来て音楽に目覚めたその子は、あの本を買って自分でマーカーを引いて、バイブルとして読んでたんです。
一一……ほんと、ありがたい話。本を出した意味を今になって感じます。
安田:その彼女をメインのイメージにして最初は創り始めた。彼女は高校生の時にWALK INN FES!に来て、そのまま太一のスタジオのスタッフになるんですけど、彼女の視点から見たWALK INN FES!っていう映画にしようと思ってたんですね。でも、途中で彼女が体調不良になっちゃって、それもそのまま脚本にしていたんだけど、あんまりそこを掘り下げても伝えたいこととずれてしまうので、一回フラットにしたんです。それで架空の少女を作って大幅変更した。でも基本的には、スタッフの女の子の目線そのままなんです。
一一架空の少女になったとはいえ、彼女の存在は重要で。ただ声だけのナレーションじゃない、ちゃんと顔のある個人として映すことに意味があるんだろうなと。
安田:ほんとそうですね。だから、彼女みたいな個人がたくさん集まってフェスを創り上げた。WALK INN FES!で人間が持つ強い意識の具現化をまざまざと見せつけられた感じがします。人間が頭で強く思うことって、実現力があると思うんです。ほんとに強く思えば、それが世の中にもたらす影響力は絶対小さくなくって。そういう個人の意思とか意識が全体に及ぼすもの、さらには個と全体の互換性みたいなものをWALK INN FES!では感じるんですね。太一はその軸を創る作業をしてるんだけど、その周りでは個々がそれぞれ自由に意識を活性化させてる。で、その集合体となったエネルギーがどこに向かうのかを、太一は自分でも楽しんでる感じがします。

野間:はははは。そうですね。自分でもわかってない。
安田:不確実な、カテゴライズできない集合体。「これはこういう集まりです」ってまとめられることを太一は否定するけど、フェスには明らかに集合体としてのエネルギーがあって。それはもう自立した個人じゃないかって思う時が、撮影していてもありましたね。フェス自体がひとつの意識。音楽ジャンルとか、関わっている人の年齢とか関係なく、ひとつの自立した意識。僕、フェスは日本に限らず世界でもいろいろ見てきましたけど、この面白さを持ったフェスってあまり見たことがなかった。それが一番、作品にしたいと思った動機だと思います。
一一わかりました。今、太一くんがやっているスタジオ経営って、日々の生活の話ですよね。そしてフェスは年に一回のハレの日になるわけで。
野間:はい。
一一その両立は、矛盾なくやれていますか。
野間:できるように、なりましたね。最初はやっぱり「なんでこんな面倒なことやんなきゃいけねぇんだ」っていう気持ちもあって(笑)。でも「やったらその先に何か見えるだろう」って思ってたから。横山さんがきっかけをくれて、やるって決めて、最初の5年は内輪に届くものをやろうと思ったんですね。僕は地元のお祭りのPAもするし、鹿児島県とか市での仕事もするから、そこで出会った業者さんたちをどんどんフェスに巻き込んでいこうって。まだブラフマンに会ったことない人たちを集めよう、Ken Yokoyamaを知らない人に見てもらおう、みたいな。だってほんとに健さんが好きな人はもうライブハウスに見に行ってるじゃないですか。
一一そりゃそうだ(笑)。
野間:去年はOAUに出てもらったけど、みんな意外と知らないんですよ。でもそこで初めて見て、ちゃんと知ってくれる。それが僕はすごく嬉しくて。じゃないとフェスの意味もないと思うんですね。ライブハウス好きな人だけが集まるならライブハウスでいい。昔のフェスってそういう理想から始まったと思うけど、途中から型が変わってきた気もするし。まぁ僕らは田舎ですからね、千人キャパでやる野外のイベントならこういうのが理想だろうなって思う。
一一この映画見たら「今度、鹿児島行ってみたい。いつかこのフェス行ってみよう!」ってなりますよ。
安田:それも目的のひとつですね。より大勢の人に見てもらう、来てもらうこと。でもさっき言った、田舎と都会の垣根を作らないっていう話もそうだけど、太一って鹿児島に落とし込めそうなものを全国から探して、素直にパクって(笑)、いい形に融合させて、毎回その変化を楽しんでるんですよ。その融合具合が絶妙だし、状況に合わせて変化し続けるタフさはWALK INN FES!が生きている証拠です。だからこれ、必死に頑張ってる田舎の話じゃなくて、居場所みたいなものを作ろうとしてるひとつの自治体のフェスとして、一番進んでる形なんだと思います。日本で一番先を行ってるのがWALK INN FES!だと(笑)。
野間:……こわっ! 80年代のハードコア撮ってきた人がこんなこと言ってますよ(爆笑)。
安田:だから、みんなもどんどん真似してやればいいですよ。

2022.09.16