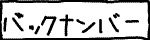フリーライター石井恵梨子の
酒と泪と育児とロック
Vol.28「ライブ・ハウスの話」
「じろじろ見たらいかんよ」
親のクルマに乗って菊川の町を通るとき、母が必ずそう言う場所があった。正方形に近い白の建物。何をする場所なのか知らなかったけれど、金色や緑色やピンク色に髪を染めた、あまりマトモには見えない人たちが入り口にたむろしていることが多く、小学生の私は「こわいふりょうだ…」と思っていた。ふりょうをじろじろ見てはいけない。小市民の鉄則である。
中学生になって音楽に出会った。きっかけは姉から教わったX JAPAN。どぎついメイク、激しいサウンド、案外聴きやすいメロディ。何がどう引っかかって、と自分でも説明できないまま、ものすごいスピードで引きずり込まれていった。初めて買った音楽雑誌。知らないカタカナがいっぱい並んでいた。ポジパン、フランク・マリノとマホガニーラッシュ、オムニバス、リッチー・ブラックモア。……えーっと、どれがバンド名ですか? わからないまま夢中で読み続けた。唯一理解できた単語はこれだった。ライブハウス。
当時のXはすでに東京ドームで興行する存在だったけれど、雑誌に載っている注目のバンドたちは、主にここを主戦場として全国を渡り歩くツアーをやっているらしい。全国にあるということは、私の住む金沢にもあるのかしら。名前と場所を調べてびっくりした。菊川のあそこだ。母が毎回見るなと言うところ。あれは、なるほど、ライブハウスというのかぁ。
行ってみたい。何度もお願いしたが毎回却下された。まだ子供だから、夜は危険だから、何があるかわからないから。だんだん理由づけも面倒になったのか、両親の言葉は「高校生になったらね」の一点張りになっていく。今ならわかる。子供の好奇心などコロコロ変わるもの。そのうち飽きるし興味の矛先も変わるとタカを括っていたのだろう。しかし、親から見れば突然始まったワケのわからない熱狂を、娘は頑なに変えようとしなかった。朝から晩までCDを聴き、不気味なくらいの熱量で音楽雑誌を読み続け、高校受験もあまり頑張らずに「制服が黒のとこ」という理由でひとつの学校に決めてしまった。「ライブハウスは黒い服で行くものらしい」。ナゾの情報を雑誌で入手し、そんなことで志望校を決めてしまえるくらいに私の中で憧れは膨らみきっていたのだ。
入学後の有言実行。初めてのライブはDEEPというバンドだった。Xのレーベルからデビューした、ロカビリーやガレージ色の強かった4人組(ベースの八田敦さんはのちにHATE HONEYに)。金沢市菊川町のvanvan V4。めちゃくちゃ怖かった、というか、何をしていいのかわからなかった。オープン前に並んでいるときも、開場してから始まるまでの1時間も、本当にどう突っ立っていればいいのかがわからない。椅子もなければ案内もなく、店員から「いらっしゃいませ」も言われない場所。こんなにも不親切な空間があるのかと驚いた。だから不安になるのだ。受付の怖いお兄さんや後ろで騒いでいるあの派手なお姉さんたちは、私のことを笑っているのではないか。この挙動不審を。このおどおどした表情を。このださい格好を……!
ファッションに興味がなかったから、自分の格好が圧倒的にださいと思ったのも初めてのことだった。普通の服なら何でもいいと思っていた。でもここでは普通と無難が超ださいのだ。こういう場所に自然と馴染んでいるお兄さんお姉さんが羨ましかった。緊張のない佇まいが、こなれた感じでタバコを吸っている表情が、それぞれの趣味趣向を感じさせるファッションが。彼らは一様に私を無視することで、ところであんた何者なんだよ、と問うているみたいだった。1993年。Tシャツ短パンの時代はまだ田舎には来ていない。
ライブの内容はどうだったんだろう。とにかく音が大きかった。バカみたいな感想。でも楽しかった。大音量に慣れておらず、翌日、翌々日まで耳鳴りが止まらなかったけど、その耳鳴りにもうっとりできるくらい楽しかった。
以来、高校では友達がまったくできなかった。全部ライブハウスで作ったから必要なかったのだ。違う高校の違う学年の、いろんな友達が音楽を教えてくれた。あとは漫画や本の選び方、粋なジョークや真似したい言い回しなど。信じられないくらい綺麗な女の子がメイクの仕方を教えてくれて、いい男の引っ掛け方も自分なりに会得した。ただし、素敵だと思っていたアマチュアのバンドマンには驚くほど金がなかった。ここは、あまりにベタなストーリーなので割愛。
ベタじゃないエピソードを探すなら、高3のときに数ヶ月間家出して、親はまず警察に連絡し、そのあとvanvan V4に「たずねびと」の紙を張りに来た、というやつがある。これは今でも酒の席でネタになる。なんで家出までしたのだろう。進路をどうするかで揉めたのだけど、とどのつまり、私はライブハウスに自然と馴染むような大人になりたかっただけなのだ。
東京に来てからも同じことの繰り返し。どう立っていればいいかわからない初めてのハコで、それを気取られないようドキドキしながら、毎回ここにいる人、のようなフリをする。初めてクラウドサーフを見たときはギョッとしたけど、田舎者がバレないように、こういうの知ってる、という顔を必死で作った。ダイバーの踵に脳天を直撃されたり、とんでもない青痣を作ったり、酸欠で死にそうになりながら、住人のフリをし続けた。続けているうちにライブハウスが私を受け入れてくれた。ハコの店長、当日のイベンター、PAエンジニアやカメラマンたちが、気づけば「おう」と笑顔を見せてくれるようになった頃に、私はようやく自分の仕事場を持てたのだと思う。音楽ライターの現場は自宅のPCなんかじゃない。少なくとも私はそう思っている。
演者ではないからステージの話はわからない。私が知っているのはフロアのことだけ。暗転と同時に「うぉぉぉ」とどよめきが起こり、人の波がぐぐっと前に移動して、ライトが点いた瞬間から誰もがたまらない表情になっているあの場所。これを待っていた! という喜びが炸裂しているのに、みんな必死すぎて、なぜだか泣いているようにも見えるあの光景。始まる直前まで、それぞれ醒めた顔をして、誰とも関わりたくないって感じでスマホをいじっているくせに、暗転の瞬間から奇跡みたいな出来事が生まれていく。25年以上通っているのにまったく飽きないのは、私が変わらないからじゃなくて、現場が日々更新されているからだ。いいライブはいつだってごく最近だった。
何度も言うけどステージの話はわからない。でも逆に、多くのバンドマンは知らないのじゃないかな。だいたいのフロアにはスイートスポットがあることを。「クアトロでステージ全体がよく見えて、音響もよく、なおかつ空調が直接当たる、どんな熱い日も涼しく鑑賞できる場所はここ」という感じ。シェルターで見るならここ。ネストならこのへんがベスト。そんな場所をハコごとに開発してきたことは私の小さな自慢でもある。フロアこそが仕事場。私のレポート原稿は常にフロアから生まれてきた。今はレポートすることがなくなって、こんな駄文を書いている。悲しいのに、昔話は妙に笑えてしまうから涙が出ない。
ギターマガジン最新号に触発され、「私とライブハウス」をテーマに何か書いてみようかなと思いました。どんなかたちでもいい。ライブハウスの話を、今後も続けていこうと思います。そして、どんな方法でもいいから、ひとつでも多くのライブハウスに生き残って欲しいと思っています。
2020.06.01